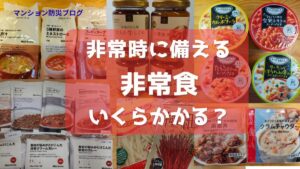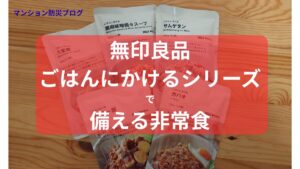「まさか自宅が浸水リスク地域だったなんて…」
とハザードマップを見て初めて気づいた。
そんな経験、ありませんか?
便利で快適なタワーマンション。
平時は災害のことからはかけ離れて、
防災について考えることはほぼなし。
でも台風や地震のたびに、不安がよぎる。
簡単に引っ越すわけにもいかない…。
ネットで調べるほど不安が増して、
「もうどうしたらいいの?」と感じることも。
でも大丈夫。引っ越さなくても、
今からできる“本気の備え”があります。
 POPPO
POPPO実際に都市部の浸水エリアに17年住んできたPOPPOの視点から、
現実的な対策と心の安心を得られる方法をお伝えするよ!
そもそも“浸水リスク”とは?ハザードマップを正しく読む


ハザードマップの色と意味を解説
ハザードマップは、各自治体が発行する災害リスクの可視化資料です。
洪水、地震、津波など災害ごとに種類が分かれていますが、
タワーマンションに住む私たちが注目すべきは
「洪水ハザードマップ」や「内水氾濫ハザードマップ」です。
色分けには意味があり、濃い色ほど浸水の深さが想定されている区域です。
たとえば「3m以上浸水」と書かれているエリアは、
1階部分が完全に水没し、車両も水に浸かる可能性があります。
特に河川のそばや埋立地などは、数十年前からの開発履歴も関係し、浸水リスクが高い傾向があります。
高層マンションがある地域でも浸水する?
「タワマンだから安心」「高層階なら水害は関係ない」
と思っていませんか?
実はそれ、半分正解で半分不正解です。
高層マンションはたしかに構造的に頑丈で、
上層階は浸水の直接被害を受けにくいです。
しかし、地下や低層部分が浸水することで、
ライフラインが止まるという重大な問題が起きます。
たとえば、エレベーター・給水ポンプ・機械式駐車場が使えなくなると、
日常生活に深刻な支障が出ます。
【実際に都心部が台風の大雨で被害を受けた際のマンション被害の実例】
エレベーターの浸水による使用不可
浸水被害による地下駐車場の使用不可
地下電源装置の水没による停電



確かに、うちは17階だから大丈夫って思ってたけど…地下施設が影響を受けて、停電したらアウトだよね…。



そのとおり!“上だから安心”じゃなく“生活の足元”に目を向けるのが大事だよ。
また、マンションの立地自体が浸水区域に入っている場合は、
地域の復旧に時間を要するので、長期的に避難が必要になることも。
都市部では、タワマンが集中する湾岸エリアや埋立地にリスクが偏っている傾向もあるので、
ハザードマップと合わせて地盤情報や自治体の防災計画も確認しておくと安心です。
「引っ越せない」からこそできる現実的な備えとは?
「すでに買っちゃったから、もう引っ越せない」
――そう思ったあなた、安心してください。
この記事で伝えたいのは、“危険を知った今から始める防災”がいちばん意味があるということです。
まずやるべきは、自宅で避難生活を送るための備え(=在宅避難)です。
タワーマンションでは、エレベーター停止や断水が発生した際、
上層階からの移動や水の運搬が非常に困難になります。
【備えているか確認してみよう】
- 飲料水や生活用水を多めに備蓄する
- 食料は加熱不要・水なしで食べられるものを中心に備蓄する
- トイレ処理袋やポリ袋を準備
- 懐中電灯・手回し充電器・ラジオなどの非常用グッズの備え



うち5人家族だけど、どれくらい水を用意すればいいのか分からないよ〜」



1人1日3Lが目安!5人家族なら15L×7日分=105Lは欲しいところだね!
関連記事|【もっと詳しく】家族の水の備蓄量と保管場所のポイントはこちら
さらに、マンションの管理組合との連携も鍵になります。
防災備蓄の有無や、非常用発電設備の稼働状況、
安否確認の体制など、共有スペースのリスクを理解しておくことで、
いざというときに慌てずにすみます。
引っ越しは無理。でも“備え”でリスクを軽減できる
引っ越せない現実があるなら、今できる備えをコツコツ進めることが安心への第一歩です。
特にタワーマンションでは「浸水」そのものよりも、
ライフラインの停止による“自宅孤立”への対策が重要です。
生活を支える電気・水・トイレの備えを整えることで、
「何もできない不安」から「備えてある安心」へと気持ちが変わっていきます。



買ったままの防災セットが押し入れの奥にあるだけで、ちゃんと備えてるって言えるのかな…?



“使える”状態にしておくのが備えだよ!中身をチェックしておこう!
停電・断水に備える家庭内備蓄の基本
停電や断水が起きると、電気ポンプ式の水道やエレベーター、冷蔵庫が使えなくなります。
備蓄の基本は「家族が1週間生き抜くためのセット」を目安にして準備しましょう。
準備しておくべきものの一例は以下のとおりです。
家庭内備蓄リスト:
- 飲料水(1人1日3L×人数×7日分)
- 加熱不要のレトルト・缶詰食品
- カセットコンロ・ガスボンベ
- 簡易トイレ(凝固剤+ポリ袋)
- LEDランタン・懐中電灯・予備電池
- スマホ充電器(モバイルバッテリー+手回し)
- ウェットティッシュ・体拭きシート
- 常備薬・絆創膏・消毒液などの救急セット



1週間分なんて場所取らないかな?冷蔵庫にも入らないし…



常温保存できる食品や“省スペース系”を選ぶのがコツだよ!
備蓄は分散保管もおすすめです。押し入れ、キッチンの棚、
ベッド下などに少しずつ分けておくことで、
取り出しやすくなり、場所の確保もしやすくなります。
関連記事|【もっと詳しく】防災用品の備蓄管理に関する記事はこちら
関連記事|【もっと詳しく】災害時には冷蔵庫の中身も上手に消費していくための記事はこちら
避難ではなく“在宅避難”の考え方
タワーマンションに住んでいると、避難所に行くよりも自宅での避難が現実的です。
なぜなら、耐震性が高く、建物に大きな損傷がない場合、
避難所の混雑を避けるためです。
避難所にはすでに多くの人が集まっており、
プライバシーや衛生面の問題もあるからです。
💡実は、東京都が発行している『東京防災』にも
「避難所だけが避難ではない。在宅避難も大切な選択肢」と明記されています。
自宅の安全が確保できるなら、慣れた環境で過ごす方が安心できる場面もあるんです。
▶️ 東京都『東京防災』のマンション防災リーフレットはこちら
だからこそ大切なのが「在宅避難」という考え方です。
在宅避難とは、建物が安全な状態であることを前提に、自宅で避難生活を送る方法です。



子どもがいるから避難所は正直きつい。できれば家にいたいなあ…



それなら在宅避難の準備を整えておこう!安全が確保できれば家の方がプライバシーなども守れるから快適だよ。
ただし在宅避難には課題もあります。
水・食料・トイレ・電気の自前確保が前提になるため、
備蓄の量・質ともにしっかり計画しておく必要があります。
また、断水時の排水問題や、ゴミ処理の方法もシミュレーションしておくと安心です。
マンションごとのルールや共有設備の確認
在宅避難の準備と同じくらい重要なのが、
マンション独自のルールや設備の確認です。
タワーマンションは戸建てとは違い、災害時に使える共有設備や、
住人同士の合意によって決まる運用ルールが多く存在します。
たとえば…
- 非常用発電機の稼働時間と範囲(エレベーターは使える?照明だけ?)
- 共用部の備蓄品(どこに何がどれだけある?)
- ゴミ置き場やトイレの利用制限(浸水時や断水時のルール)
- 管理会社や管理組合との連絡手段(掲示板?メール?防災アプリ?)



そういえば、うちのマンションって防災訓練とかあったっけ…?知らないこと多いかも…」



今からでも管理組合に確認してみよう!“知らなかった”が命取りになるかも。
また、近隣住民とのつながりも災害時の心強い支えになります。
普段は挨拶程度の関係でも、いざという時に声をかけ合える相手がいるだけで安心感が違います。
掲示板や自治会の集まりに一度だけでも顔を出しておくと、
いざという時にスムーズに連携が取れるかもしれません。
今からできる“3つの備え”で不安を行動に変える
「引っ越せないし、マンションだし…どうしよう」と悩むより、
今できる備えを一つずつ進めることが安心への第一歩です。
何から手をつければいいかわからない…という方も、
まずは次の「3つの備え」から始めてみましょう。
防災品を備える:家庭内の備蓄を“見える化”して整える
まず最初は、家庭内の備蓄を“見える化”すること。
頭の中で「たぶんある」ではなく、リスト化して把握することで、
必要なもの・足りないものが見えてきます。
やることチェックリスト:
- 飲料水と食料を人数×7日分そろえているか
- カセットコンロ・トイレ袋などの“使用ツール”があるか
- 子どもの成長に合わせてサイズが合っているか(オムツや靴など)
- 食品の賞味期限や電池の残量を確認しているか
- 「非常用」と決めた保管場所にまとめてあるか
備蓄は完璧を目指さなくてもOK。
まずは必要量を把握→足りない分を買い足す
→定期的にチェックという流れをつくることがポイントです。
関連記事|【もっと詳しく】非常食の管理でお困りならこちら
再会を備える:家族と話し合って“マイルール”を決めておく
災害は、いつ・どこで起こるか予測できません。
だからこそ、いざというときの家族内ルール(=マイルール)を決めておくことが大切です。
たとえば、地震発生時に子どもが学校・親が職場にいると、連絡がつかない可能性があります。
その時に「誰がどこに集合するか」「何時間待っても来なければどう動くか」などを事前に話し合って決めておくと、慌てずに済みます。



スマホが繋がらない状況が本当に怖いよね。



最悪のケースでも対応できるように話し合って決めておくことは本当に大事だよ。
考えておきたいマイルールの例:
災害時の集合場所・避難場所
家族間の連絡手段(スマホが使えない時の対策)
子どもだけで自宅待機する際のルール
家族で防災について話すこと自体が、防災意識を育てる一歩になります。
とくに子どもがいる家庭では、「自分で考えて動ける力」を育てる機会にもなりますよ。
関連記事|【もっと詳しく】災害時に家族と再会する方法の記事はこちら
知識を備える:地域のハザードマップや地盤情報を今すぐチェック
「買ってしまったマンションが浸水地域だった」と気づいたとき、
まずやるべきことは“正確な情報を把握すること”です。
なんとなくの不安ではなく、
自分の住む地域が実際にどんな災害リスクを持っているのか、
事実を知ることで冷静な判断ができるようになります。



うちって川が近いけど、どのくらい危ないのか正直よくわからない…



“見える化”すると不安も具体的に対処できるようになるよ!
今すぐチェックすべき情報:
- 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」
→ 土砂災害・洪水・高潮などを地図で確認 - 地盤サポートマップ(住宅地盤の揺れやすさを色分けで表示)
- 自治体の防災情報ページ(地域別の避難所、災害履歴など)
- 分譲時のパンフレットや管理組合の資料(建築地の地盤や災害想定)
これらの情報を確認したうえで、
「ここに住み続ける場合の備え」を具体的に計画できます。
もし引っ越しを検討するなら、それも冷静に判断する材料になります。
【FAQ:よくある質問】
- Q1. タワーマンションが浸水地域にあると知ったら、すぐ引っ越すべき?
-
A. 必ずしもすぐに引っ越す必要はありません。建物自体が浸水しない高さにある場合でも、ライフライン停止などのリスクには備える必要があります。在宅避難や備蓄をしっかり整えることで、安全に住み続ける選択も可能です。
- Q2. 在宅避難と避難所避難、どちらが安全?
-
A. 建物の構造や被害状況によりますが、高層マンションでは在宅避難の方が安全かつ快適な場合も多いです。ただし、電気・水・トイレなどの備えが不可欠です。避難所の状況も事前に確認しておきましょう。
- Q3. 非常用の備蓄って、どこに保管するのがベスト?
-
A. キッチンの一角、ベッド下、押し入れなど、複数の場所に分散保管するのがベストです。非常時に一か所が使えなくなっても他から取り出せるようにしておきましょう。
- Q4. 子どもがいる場合、どんな備えが必要?
-
A. 食料・水の量はもちろん、サイズに合った衣類や靴、オムツなどを定期的に見直しましょう。また、災害時の行動ルールを親子で事前に話し合っておくことも重要です。→【家族と再会するためのマイルールはこちら】
- Q5. ハザードマップや地盤の確認ってどうやるの?
-
A. 「ハザードマップポータルサイト」や「地盤サポートマップ」で自宅周辺の災害リスクを視覚的に確認できます。自治体の公式サイトにも避難所や防災計画の情報があります。
在宅避難に備えるためにおすすめしたい防災グッズ
都市部のタワーマンションで災害時も「在宅避難」を選ぶには、
自宅内でライフラインが止まっても生活できる備えが必要です。
ここでは、実際に役立つと感じたアイテムを厳選してご紹介します。
【PR】電気が止まってもスマホやライトを使える「Jackery ポータブル電源」
💡おすすめポイント:
- 停電時でもスマホの充電・LEDランタン・扇風機に活用可能
- ソーラーパネル併用で長期停電にも対応
- USB・ACコンセント対応で汎用性◎



エアコンは無理でも…扇風機くらいは動かせると安心感あるかも!



中容量モデルがおすすめだよ。夜間の灯りや情報収集にも!電源は備えてると本当に安心。
▼参考価格帯: 45,000円〜80,000円(容量により異なる)
▼販売先: 公式サイト、Amazon、楽天
※ふるさと納税の返礼品に採用されている自治体もあります!
【PR】断水でも安心!「非常用トイレセット(凝固剤+袋タイプ)」
💡おすすめポイント:
- 水が流れなくても使える簡易トイレ
- 1日あたり大人1人5回使用を想定し、1週間分を目安に
- 凝固剤は消臭・抗菌タイプを選ぶと安心
▼参考価格: 1人7日分セット 約3,000円〜
▼購入先: LOHACO、Amazon、防災専門ショップなど
【PR】マンションでも食事を確保「尾西食品 アルファ米セット」
💡おすすめポイント:
- 水orお湯で戻すだけ、火が不要
- 5年保存で備蓄に最適
- チャック付きでゴミ処理もしやすい



レトルト系ばっかりじゃ飽きそう…子どもが食べてくれるのかな?



アルファ米なら味の種類も豊富!カレーや五目ご飯もあるよ!
▼価格帯: 12食セット 約4,000円〜
▼販売先: Amazon、公式サイト、ふるさと納税などで取り扱いあり
▶️ 【PR表記】この記事にはアフィリエイトリンクを含みます。リンクからのご購入で運営者に報酬が発生する場合があります。
【まとめ】ハザードマップで不安になったあなたへ。今できる備えを始めよう
今回の記事では、以下のような内容をお伝えしました。
この記事の要点まとめ
- ハザードマップで危険地域と知っても「引っ越し一択」ではない
- タワマンでの在宅避難には備えが必要(電気・水・食料・トイレ)
- 家族で“我が家の防災ルール”を話し合うことで安心が増す
- ハザードマップ・地盤情報をもとに、具体的な対策を立てよう
- 専門家も推奨するポータブル電源・非常用トイレ・備蓄食の活用が有効
「住む場所」は簡単に変えられないからこそ、備えが自信と安心につながります。
「知らなかった」「想定してなかった」と後悔しないよう、今できる小さな準備から始めましょう。
\ 家族と5分、防災について話してみよう /
「どこに逃げる?」「何が困る?」小さな会話が大きな命綱になります。
住まいがハザードマップで「浸水リスクあり」とわかっても、すぐに引っ越す必要はありません。重要なのは、地域特性を把握し、適切に備えること。上層階にいるからと安心せず、停電・断水・孤立への対策が必須です。家族で避難の選択肢や備蓄を考え、「行動できる備え」を今から始めましょう。
紹介リンクのまとめ