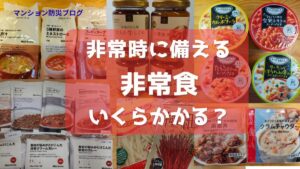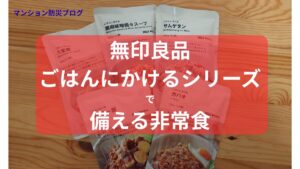こんなとき、どうしたらいい?
「うちは冷凍庫に食材がたっぷり入ってるし、防災もある程度意識してるから安心…」そんなふうに思っていませんか?
でも、もし停電したら?冷凍庫も冷蔵庫もただの箱。せっかくの食材があっという間に傷んで、ゴミになる可能性も…。
私自身、防災オタクとして多くの人に「冷凍=安心」は実は落とし穴だと伝えたいのです。
この記事では、家庭の冷凍庫を“非常食庫”に変える方法をお伝えします。普段の買い物や下ごしらえをほんの少し変えるだけで、停電時でも安全・簡単に家族のごはんを守れる。防災食は特別じゃなくていい、日常から始める備えのヒントがここにあります。
結論から言うと…
災害時、冷凍庫や冷蔵庫の食材は「停電後2日以内に使い切る」が基本です。
普段から食材を下味・カット・半分調理して冷凍しておくことで、非常時でも湯煎調理やそのまま加熱で安全に食べられます。
特別な防災食を買うより、“普段のズボラ備え”がいちばん頼れる防災術です。
冷凍庫の中身、非常時にどうなる?知らないと損する冷蔵庫の落とし穴
「うちの冷凍庫はパンパンに詰まってるし、災害が来ても数日くらい大丈夫でしょ」と思っている方、少なくないのではないでしょうか。でも実は、停電した瞬間から冷蔵庫も冷凍庫も“劣化”が始まっているんです。
冷蔵庫が停止すると、扉を開けるたびに温度が上がり、食品の劣化が早まります。特に夏場は6時間以内で痛み始め、24〜48時間が腐敗のタイムリミット。冷凍庫も例外ではなく、開閉を抑えても2日以内には自然解凍が始まってしまいます。
つまり、「入っていれば安心」ではなく、“どう使い切るか”を決めておくことが本当の備えなのです。
 まんボ
まんボ冷凍庫の中身がゴミになるなんて…考えたくないよね。



でも、ちょっとした工夫で冷凍庫が防災の味方になるんだよ!
停電時の冷蔵庫・冷凍庫の保存限界は何時間?
冷蔵庫は扉を閉じていても8時間〜12時間、冷凍庫でも約48時間が限界とされています(冷凍庫は内容物が詰まっているほど保冷効果が持続)。
ただし、これは「開けない」前提の話。何度も開け閉めすると、あっという間に庫内温度は上昇します。
特に以下のタイミングは要注意です。
- 停電が発生した直後
- 食材を取り出すとき
- 停電が復旧したかどうか確認するとき
できる限り開けないことを心がけましょう。
冷蔵庫・冷凍庫の保存限界まとめ:
| 庫内タイプ | 保存可能時間(目安) | 注意点 |
|---|---|---|
| 冷蔵室 | 約4〜8時間 | 開けない、温度上昇早い |
| 冷凍室 | 約24〜48時間 | 詰まってるほど長持ちする |
| チルド室 | 約2〜4時間 | 最も早くダメになる |
冷凍食材が腐る前にどう活用するか
冷凍食材は保存性が高いですが、自然解凍が始まると細菌の繁殖も一気に進みます。その前に、できるだけ簡単な手順で使い切ることが大切です。
たとえば…
- 湯煎で温めるだけのパスタやチャーハンはすぐ活躍
- 下味済みの肉・野菜ミックスはポリ袋ごと加熱OK
- ハンバーグや炒めミンチなどはそのまま加熱して食べられる
食べやすさと調理のしやすさを事前に確保しておけば、非常時でも安心です。



冷凍って万能と思ってたけど、使い方次第なんだね。



腐らせる前提じゃなく、“食べ切る計画”が大事なんだよ。
よくある誤解「冷凍庫にある=備えになる」は危険
「冷凍庫にお肉あるし、冷凍うどんもたくさんあるし大丈夫!」
そう思って安心していませんか?実はこの考え方、災害時には危険です。
なぜなら、停電時に「その冷凍食材をどうやって調理・解凍するか」の準備ができていないと、使えないどころか腐ってしまうから。冷凍庫が“使えない箱”になってしまうリスクを考えるべきです。
また、冷凍食材は調理器具や水の確保も必要。水道やガスが止まっていると、食べる方法すらなくなってしまうかもしれません。
「備えたつもり」が一番危ない。本当の備えとは、「食べ切るプラン」「調理可能な形」まで考えてこそ成り立つのです。
関連記事 | 非常食の保管方法に関する記事はこちら
冷凍庫を“非常食庫”に変えるために必要な3つの工夫
非常時に使える冷凍庫へとアップデートするには、ただ食材を詰めるだけでは不十分です。重要なのは「どう調理するか」がイメージできる状態にしておくこと。
そのためには、次の3つの工夫がカギになります👇
下味をつけて冷凍する
半分調理した状態でストック
カット済みで調理レス化を図る
この3ステップで、調理の手間を減らし、湯煎やポリ袋加熱などでも安全においしく食べられる状態を作っておくことができます。



冷凍してるけど、調理のことまでは考えてなかったかも…



少しの下ごしらえで、災害時も“食べる”を守れるんだよ!
下味で冷凍、加熱で即食べられる仕組み
下味(下ごしらえの味付け)をした状態で冷凍しておくと、災害時の調理が圧倒的にラクになります。
塩こうじ、焼肉のたれ、味噌などの調味液に漬け込むことで、解凍時にうまみが染み込んだ状態で調理が可能。特に一口大に切った鶏むね肉や豚こまなどは、味付きで柔らかく仕上がりやすくおすすめです。
以下のような味付けが非常時に活躍します。
- 塩こうじ+ごま油:和風炒めや焼き用に
- 焼肉のたれ+ケチャップ:子どもにも人気な甘辛味
- 味噌+みりん:焼くだけでおかずになる万能味
- 砂糖+醤油+お酒:ホッとする純和風の甘辛味
- オリーブオイル+塩:好みでハーブなど入れても◯
「ポリ袋調理」や「ホットプレート調理」にも向いているので、加熱だけで一品完成する便利さが魅力です。
半分調理しておくと湯煎で復活できる
「半分調理」とは、加熱工程の半分を済ませた状態で冷凍保存するテクニックです。
例えば…
- 合い挽きミンチと玉ねぎを炒めておく
- 鶏肉を蒸し鶏にして火を通してから冷凍する
- 炒めた野菜とソースを混ぜてパスタソース化しておく
- 茹で豚を作ってスライスして冷凍しておく
こうすることで、湯煎だけで復活させることが可能。特にガスや電気が止まった時、カセットコンロや保温ポットで調理できる手段があるのは安心材料になります。



冷凍しても“加熱しないと食べられない”って大変かも…



調理過程を半分済ませておくだけで、災害時もラクになるよ!
カット済みで調理レス!非常時こそ便利な形状とは?
非常時には“包丁を使わない”が正義です。
だからこそ、あらかじめカットして冷凍保存しておくことが、非常に役立ちます。
以下のような形状・状態での保存がおすすめです👇
- 【一口サイズ】の肉や野菜(加熱しやすい&食べやすい)
- 【スライス済み】玉ねぎ・きのこ(味噌汁や炒めものに便利)
- 【小分け冷凍】使いやすい量をポリ袋に入れて冷凍
カット済み食材は、ポリ袋に入れたまま湯煎、炒めるだけ、煮るだけで使えます。
また、まな板・包丁がなくてもOKな点は、災害時の大きなアドバンテージになります。
このように「下味・半分調理・カット済み」という3段階で冷凍庫を準備することで、停電時にも“調理できる非常食”として最大限活用することができます。
冷凍庫の活用法:非常時にも使えるズボラ料理テク大全
「災害時=特別な準備が必要」と思っていませんか?
でも実は、普段から“ズボラ”にやっている時短調理の工夫こそが、非常時に強いんです。
調理済み、半分加熱済み、冷凍ストック、湯煎だけで食べられるレシピ…それらは非常時にこそ輝きます。
このパートでは、我が家で実際にやっている冷凍テクをもとに、子どもでも扱いやすく、かつ非常時にも役立つズボラ料理の工夫をまとめてご紹介します!



ズボラごはんが防災になるなんて…ほんと?



うん、ラクしながら備えになるって最強じゃない?
ズボラ調理とはいうけれど、先に下準備して冷凍しておくっていうスタンスだよ。
ハンバーグ・ミンチは炒めて冷凍が最強説
ハンバーグや炒めたミンチは、実は防災にも超優秀な冷凍食材です。
なぜなら、以下のような特徴があるから👇
- 火が通っている状態で冷凍できる
- 湯煎やポリ袋調理だけでそのまま食べられる
- お弁当や子どもごはんにも使える万能さ
- 味のバリエーションをつけやすい(和風・洋風・中華)
たとえば、合い挽きミンチを炒めて塩こしょうだけしておけば、
チャーハンやパスタ、うどんにも使える“ベース肉”として機能します。
ハンバーグは冷凍してもジューシーさが保たれやすく、加熱再現性が高いのも嬉しいポイント。
パスタ・チャーハンは湯煎用ラップ保存が便利
冷凍パスタやチャーハンは、1人前ずつラップに包んで冷凍保存しておくと、
そのまま湯煎で温めるだけで立派な1食になります。
おすすめなのは👇
- 炒めてからラップ包み → 冷凍 → 湯煎(またはレンチン)
- 子ども用に味を薄めにして作っておく
- あらかじめ具材を小さくして混ぜ込むと食べやすい
特に「ポリ袋調理」に慣れていれば、お湯があれば完成する食事になるのは心強いですね。



我が家は既製品のチャーハンやパスタもストックしてるんだけど。



それもポリ袋にいれて湯煎して温めるといいよ。
手軽に食べられる温めるだけの冷凍食品も活用したいね。
冷凍おかずのざっくり仕分けと私流ルール
いくら備えても、何がどこにあるか分からない状態では活用できません。
だからこそ、仕分けはとても大切です。とはいえ、そんなに真面目にはやりません。
我が家では次のようなルールを決めています👇
- 月に1回お肉を買って、下処理をする
- ポリ袋に入れ、さらにジッパー付きの袋に入れて整理
- 子供達が使うものは所定の位置を決めて保存
- ラベリングはしない代わりに、肉類・野菜類・炭水化物類などざっくり分類
雑誌に出てくるような、マステを使用してラベリングなんてしません。
作る種類も定番があり、冷凍庫に入っているものは毎月同じ。月に1度に作りかえる程度です。
冷凍庫=パントリーとして使うつもりで、見える化しておくのがコツです!
冷凍庫防災術を実践する前に知っておきたい3つの注意点
「よし、冷凍庫を非常食庫にしよう!」と意気込む前に、いくつかの注意点を押さえておくことがとても大切です。
間違った保存方法や、停電時の対応ミスが、せっかくの準備を無駄にしてしまうことも…。
ここでは、冷凍保存で防災対策を始める前に「これだけは知っておいて!」という3つの注意ポイントを紹介します。



頑張って備えたのにダメにしたら…悲しすぎるよね



そうそう!始める前にチェックしておけば失敗しないよ!
冷凍できない食材と注意が必要な調味料
この見出しの本文:(400文字で作成), [text+list]
実は、冷凍に向かない食材や、味が変質しやすい調味料もあります。
とくに以下のものは注意です👇
【冷凍に向かない食材・調味料】
- 生野菜(特に葉物・水分の多いもの):
レタス、きゅうり、白菜、なす、ピーマン、セロリ、水菜、サラダ用の野菜などは、解凍後に水分が抜けたりぐずぐず・べちゃべちゃになり、食感も味も大きく損なわれます。 - 根菜類(一部を除く):
じゃがいも、ごぼう、たけのこ、大根、人参など。解凍すると筋っぽくなったりスカスカになります。 - 豆腐・こんにゃく:
豆腐やこんにゃくは、冷凍→解凍するとスカスカ、ゴワゴワなど全く異なる食感になります。 - 卵:
生卵を殻のまま冷凍はNG(膨張して割れる)。調理済みの卵もパサパサして食感が悪くなります。 - 一部乳製品・チーズ:
リコッタやクリームチーズなどソフトチーズは解凍後に分離しやすい。 - マヨネーズ・ケチャップなどエマルジョン・ソース類:
卵と油が分離し、ダマや水っぽくなります。
こうした食材は加熱してから冷凍するか、冷凍以外の備蓄法を選ぶのが賢明です。
停電中に冷凍庫を開けない方がいい理由
停電が起きると、つい冷蔵庫を開けて確認したくなりますよね。でも、それはNGです。
1回開けるだけで庫内の温度は一気に上昇し、冷気が逃げてしまうからです。
特に冷凍庫の場合、開けるたびに“持ち時間”が短くなると考えてください。
庫内に保冷剤や冷凍ペットボトルを入れておくと温度を下げやすいですが、それでも開閉は最小限に抑えるべきです。



冷凍庫開けるの、クセになってるかも…



停電中は“開けたら終わり”くらいの気持ちで閉じておこう!
冷蔵庫が完全停止する前にすべき行動チェックリスト
災害が予測されているときや停電の可能性があるときは、事前にやっておくべき準備があります。
以下のチェックリストを確認しましょう👇
🔳 冷蔵庫チェックリスト(停電前)
- 冷凍庫に保冷剤を追加しておく
- ペットボトルに水を入れて凍らせておく(保冷源になる)
- 開けなくても良いように中を把握しておく
- カセットコンロの燃料チェック
これらを実践するだけで、停電時の冷蔵庫の保冷力がかなり変わってきます。夏場はペットボトルを冷凍庫に入れる余裕があれば、ぜひ取り入れてほしいです。
“停電後”に慌てるのではなく、“停電前”にできることをやっておくのが冷静な備えです。
関連記事| 災害時の調理に関する記事はこちら
家庭で今日からできる!冷凍庫を活かした防災ステップ
ここまで読んで、「やってみようかな」と思ったあなたに向けて、“今日からできる”実践ステップを紹介します!
冷凍庫の中を一気に変える必要はありません。
日々の買い物・調理の中にちょっとした意識を加えるだけで、
非常時にも頼れる冷凍庫へと自然にアップデートされていきます。
この章では、「何から始めればいいか」「どう習慣にするか」を
主婦目線・育ち盛りの子どもがいる家庭を想定してお伝えします。



結局どう動けばいいか分からないんだよね〜。



順番にやれば大丈夫!一つずつ備えを積み重ねていこう!
週1の冷凍ストックルールの作り方
我が家では、「月に1回だけストックDAY」を設けています。食材別に冷凍していくので、各1回で4種類程度で週1回ほど冷凍保存を行なっていきます。
やることはとてもシンプル👇
- 安い野菜を多めにカットして冷凍(小分けで)
- 肉は味付け・漬け込みしてから冷凍
- 1回で1ヶ月分作るのではなく、豚肉・牛肉・鶏肉・野菜など分けて作成する
これだけで、平日の食事準備もラクになり、
災害時にも「食材がある」「すぐ食べられる」という安心が得られます。
継続のコツは“やりすぎない”こと。
ストイックすぎず、ゆるく続けられる自分ルールが◎。



市販の冷凍野菜をストックするのもいいね〜。玉ねぎのみじん切りとかすごい楽なんでよね。



POPPOは行きつけのスーパーで豚肉の日・牛肉の日なんて決まってるので、その日にまとめ買いして仕分けして冷凍してるよ。
季節の野菜も安いので、多めに買った時は冷凍保存して時短調理!
子ども用の自炊キットを冷凍庫に準備する方法
非常時には、大人が不在だったり動けなかったりする場面も考えられます。
そんな時のために、子どもが一人でも食べられる「自炊キット」を冷凍庫に用意しておくのがポイントです。
たとえば…
- パスタ・チャーハンを1人前ずつラップ冷凍(市販品も活用OK)
- スープ用の具材とスープの素をセットで保存
- ラップ済みおかず(お好み焼き・ハンバーグなど)
- ホットケーキは多めに焼いて冷凍
普段から、お子さんが調理できるように自宅で簡単クッキングは一緒にしておくといいです。日頃の慣れが、非常時にも活かされます。



子どもが自分で調理できるなんて、食育にもなるね〜🎵



夏休みや休日のお昼などに一緒に始めるのがおすすめ。
慣れると子どもだけでも調理してくれるよ!
火の元や家庭のルールはきちんと決めてから使うのも忘れずにね。
3日分の食事を1日で仕込む時短テクニック
我が家のルールは「3日分の主菜は1日で仕込む」。
これは、災害時の備えであると同時に、平時の時短術でもあります。
冷凍に向かない野菜はカットして冷蔵保存
→ もやし・レタス・きゅうりなど、食感が変わりやすい野菜は冷蔵で保存。数日で使い切る前提。
煮物系の主菜(肉じゃが・筑前煮など)は冷蔵保存が前提
→ ごぼう・にんじん・じゃがいもなど冷凍に向かない野菜が多いため、調理してから冷蔵へ。
→ 肉は冷凍庫にストックがあるので慌てず調理可能。
主菜用の漬け込み肉・魚は冷凍庫へスタンバイ
→ 下味をつけて冷凍保存しておけば、当日は焼くだけ。
→ 付け合わせはその日の気分でざっくり用意。時には冷凍野菜や残り物で十分。
副菜は2〜3品まとめて作り置き、冷蔵へ
→ 小鉢やお弁当にも使える常備菜を意識。簡単な和え物や炒めものがおすすめ。
買い出しで多めに買った食材はこのタイミングで冷凍保存追加も
→ 安かった旬の野菜やまとめ買いした肉類は、カット・下味・小分けして冷凍庫へストック。
こうしておけば、平日もフライパンで焼くだけ、レンジで温めるだけで食事が完成!メインを作っている間に冷凍の野菜を使ってお味噌汁も簡単に出来上がり!
災害時にも、ガスや水が止まっていてもカセットコンロ+湯煎で対応可能になります。
“ズボラ=備え”になる最高の時短習慣、ぜひ取り入れてみてください。
FAQ
Q1. 停電したら冷凍庫の中身はどれくらい持ちますか?
A. 冷凍庫は扉を開けなければ24〜48時間が目安です。保冷剤や凍らせたペットボトルで持ち時間を延ばすことができます。
Q2. 冷凍しておけば何でも保存できる?
A. いいえ。水分の多い野菜やマヨネーズなどの調味料は冷凍に不向き。食感や風味が損なわれる場合があります。
Q3. ポリ袋調理って危なくないの?
A. 耐熱性ポリ袋を使えば安全に調理可能です。必ず耐熱温度を確認し、密閉しすぎないよう注意してください。
Q4. 子どもでも扱える冷凍ごはんってある?
A. 普段はレンジで加熱して食べられるチャーハンやパスタ、小分けしたお好み焼きなどがおすすめ。一緒に作って練習もある程度はしておきましょう。
Q5. 何から始めればいい?
A. まずは冷凍庫内の把握と整理。次に、週1回の冷凍ストック日を作ると習慣化しやすいです。
まとめ:冷凍庫は「非常食庫」に変えられる!
今回の記事では、冷凍庫を非常時に活用するための具体的な工夫と注意点を紹介しました。
以下に要点をまとめます👇
要点まとめリスト
- 停電後の冷凍庫は2日以内が勝負。腐る前に使い切る意識が重要
- 「下味・半分調理・カット済み」で非常時にも使いやすく保存
- ズボラ料理が防災に直結する!湯煎・簡単調理を前提に冷凍
- 停電時は“開けない”が基本。保冷剤・冷凍ペットボトルを活用
- 週1の冷凍DAY・子ども用自炊キットで家族全員が備える体制に
冷凍庫をただの保存庫ではなく、「非常時にも動ける備蓄庫」に変えるのはいかがでしょうか?
今日からでも、少しずつでも始められます。
冷凍=備えの第一歩。
ズボラに見せかけた週1の冷凍ストックを試して、平日の食卓も災害時の備えも一石二鳥で叶えましょう!
関連記事 | 非常食の選び方に関する記事はこちら